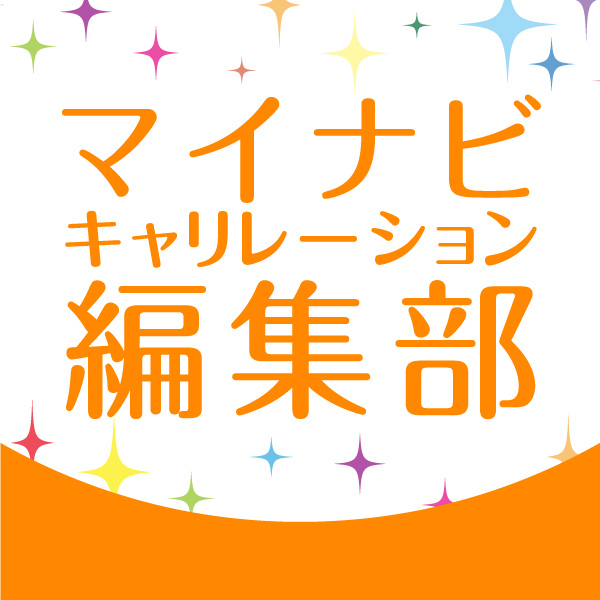妊娠がわかったとき、職場へはいつ報告する?上司や同僚への伝え方を解説!
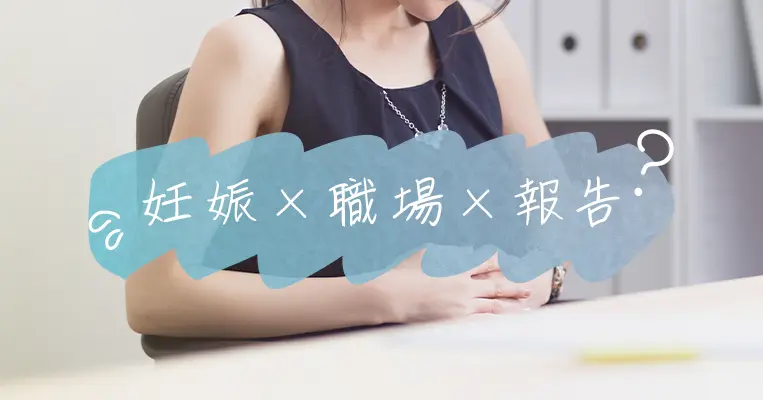
妊娠はとてもおめでたい出来事ですが、働いている妊婦さんには「仕事をどうする?」「職場にはどう言う?」という悩みも同時にやってきます。この記事では、職場に妊娠を報告するタイミングや、伝え方、注意する点などについて詳しく解説していきます。
妊娠の報告はいつするべき?
職場に妊娠を報告する時期について、法的な決まりなどはありません。ベストなタイミングは、一人ひとりの妊娠の経過や職場の状況によっても異なりますが、現在は大半の人が、妊娠2~3ヵ月程度の初期に職場の上司などへ報告することが多いようです。
かつては、職場に妊娠の報告をする時期は、一般的に安定期と言われる妊娠5ヵ月(妊娠16週以降)を迎える頃が適していると言われていました。なぜかというと、妊娠初期は自然流産が多いためです。流産は珍しいことではなく、妊婦さん全体の15%程度が経験すると言われています。そして、その8割は妊娠12週までに起こります。そのため、「妊娠の報告をした後日、流産の報告をする」という状況を避けるために、安定期まで報告を待つ人が多かったのです。
しかし、妊娠中は何があるか予測できません。つわりが軽くて妊娠前と同様に働けると思っていても、体調が急変する場合もあります。決して無理をせず、妊娠がわかったら早めの段階で職場へ報告することをおすすめします。
安定期よりも前に報告した理由
早い段階で職場に妊娠を報告した人が挙げている理由の多くは、「業務内容や勤務体系を変更してもらうため」です。
重い物を持つ、高いところに上る、危険物を扱うといった仕事や、夜勤などの不規則な勤務、外回りや立ち仕事が中心で負担の大きい仕事は、母体を危険にさらしてしまうことがあります。つわりなどで体調が安定しないときには、ラッシュ時の通勤なども負担が大きいでしょう。こういったケースで妊婦が困難な状況を申し出たときには、職場が必要な対応を取るよう男女雇用機会均等法で定められています。
なお、たとえ業務内容や体調に問題がなくても、長期のプロジェクトに携わっている人や将来携わる予定がある人は、代わりの要員が確保できるよう、早めに上司に相談する場合が多いようです。
上司への報告の仕方
職場で妊娠の報告を最初にすべき相手は上司です。業務内容や勤務体系の変更、通院や体調不良時の配慮などを求めたいときは、まず上司に状況を理解してもらう必要があります。また、産休や育休を考えている場合も、退職を考えている場合も、業務の調整や人員確保のために動かなければならないのは上司なので、現時点でのあなたの希望をしっかり伝えましょう。
なお、あなたが派遣社員の場合、直属の上司は「派遣会社の担当者」です。派遣先企業に誰から、いつ、どのように伝えるかは、派遣会社の担当者に相談しましょう。
上司に報告するときは、あらかじめアポイントをとって、ほかの人のいない会議室などで直接伝えるのがベストです。
チームのメンバーや同僚にはいつ、どのように伝えればいい?
チームのメンバーや同僚にいつ伝えるかは、上司に報告する際に相談しておくといいでしょう。伝えるタイミングはケースバイケースです。
業務の変更や頻繁な欠勤などで周囲のサポートが必要な場合は、理由を伝えた方が納得して助けてもらえる場合もあります。もしこれまでと変わりなく勤務できるのであれば、安定期に入ってからの報告でも問題ないでしょう。代わりの人員が採用できた段階でチームに伝えるケースもあります。
チームのメンバーや同僚に伝える際は、朝礼やミーティングなど関係者が集まった場で、自分の言葉で直接伝えるのがいいでしょう。同じタイミングで関係者全員に伝えれば、自分の望まない形でいつの間にか噂が広がるのを避けることができます。
上司に報告する前に準備しておくこと
上司に妊娠を報告するときは、どんな反応が返ってくるのか誰でも不安だと思います。一方、上司の側も「いつ部下から妊娠を報告されるか」「部下が妊娠したら業務をどう調整しようか」と不安に思っているものです。
不安に思うのは、先の見通しが立たないからです。上司に妊娠を報告する前に、今後についての情報をまとめておくと、あなた自身と上司の安心に繋がります。今後の見通しを上司と共有し、双方の今後の動きについて合意できるよう、以下のことを準備しておきましょう。
産休・育休制度の確認
まずは産休(産前産後休業)・育休(育児休業)の制度について知っておきましょう。産休・育休はいずれも法律で定められた制度です。
産休(産前産後休業)は、出産前後の女性が利用できる休業で、職場に申請することで出産予定日の6週間(42日)前、多胎妊娠の場合は14週間(98日)前から取得できます。産後休業は雇用者側の義務で、従業員が出産したら原則8週間(56日間)は休ませなければなりません。ただし、本人が希望して医師の許可があれば、産後6週間以降に職場復帰させることができます。
育休(育児休業)は、男女問わず取得できる、育児のための休業制度です。原則として子どもが1歳になるまで(条件により最長2歳まで)取得可能です。
産休・育休の申請方法は職場によって異なります。また、勤続1年未満の人や勤務日数が少ない人、登録型の派遣社員、契約社員、パート、アルバイトなどの場合は、制度の対象外となる場合もあります。就業規則を読む、人事に問い合わせるなど、事前に調べておきましょう。
無期雇用派遣でも産休は取れる?
無期雇用派遣は、一般的な登録型派遣(有期雇用派遣)とは異なり、契約更新がなく派遣会社に常時雇用される働き方です。無期雇用派遣スタッフは、勤続期間などの条件を満たせば、正社員と同様に産休・育休を取得できます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
産休開始までの引継ぎスケジュールや、職場復帰時期の希望
上司にとって最大の関心事は、あなたがいつまで働けるか、あなたが現在担当している業務を産休・育休の期間中どうするかという点です。上司がチームの業務の調整や、代替人員の確保をスムーズに行えるよう、以下の項目を明確にしておきましょう。
- 出産予定日
- いつまで働けるか(産前休暇の開始日)
- 職場復帰の意志と希望時期(育休をいつまで取得したいか)
- 現在の担当業務を引き継ぐ相手(いない場合は採用の希望など)
- 引継ぎのスケジュール(代替人員をいつまでに採用する必要があるか)
なお、産休・育休は、出産後に仕事を職場復帰する前提がなければ取得することができません。退職を考えている場合は、まずそのことをしっかり伝えましょう。
その他、業務や通勤に関する配慮の希望など
現在の仕事が母体に負担のかかる内容の場合や、つわりなどで体調が安定せず業務に支障が出そうなときは、業務や配置の転換、時差出勤や在宅勤務の必要性など、要望をまとめておきましょう。
あなたの現在の体調と、職場に求める配慮について、あらかじめ医師に「母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)」を書いてもらって用意しておくと安心です。
上司へ報告する際の例文
必要な情報をそろえたら、上司に連絡してアポイントを取りましょう。
当日どんなふうに話せばいいかイメージをつかんでいただくために、口頭で伝える場合の例文と、報告のポイントをご紹介します。
お忙しいところお時間をいただきありがとうございます1。
ひとつご報告があります。実は現在妊娠〇ヵ月で、出産予定日は〇月〇日です2。
産後も仕事を続けたいと考えており、〇月〇日頃から産休に入らせていただけるとありがたいです3。
産後は、子どもが1歳の4月に保育園に入れ、職場復帰したいと考えています。もし年度途中の入園が可能であれば、早めの復帰も検討したいです4。
現在担当している〇〇の業務は〇〇さんへ、〇〇の業務は〇〇さんへ、〇月までを目途に引継ぎたいと考えています5。ただし、今よりも少ない人数で同じ量の業務を回すのは厳しいと思いますので、人員増などご検討いただけますでしょうか6。
なお、現在つわりのためとても疲れやすく、吐き気やめまいなども出ている状況です。デスクワークにはそれほど支障がないのですが、電車での通勤がとても負担になっています7。医師からは、切迫流産のリスクがあるため体調が落ち着くまでは在宅勤務中心にするよう指導されています。認めていただけますでしょうか8。
チームの皆さんには引継ぎなどで負担をかけることになり大変心苦しいのですが、産休までの間、できる限りの貢献をしていくつもりです。どのタイミングで皆さんに伝えるかについては、ご相談させてください9。
【報告のポイント】
-
- まずは自分のために時間を取ってくれたことに対する感謝を伝えます
-
- 事実として、妊娠したことと、出産予定日を伝えます
-
- 仕事を続ける意志と、休業の希望について伝えます(退職予定の場合は、退職したい旨と希望の時期を伝えます)
-
- 仕事を続ける場合は、職場復帰時期の希望を伝えます
-
- 現在担当している業務を引き継ぐ相手について伝えます。誰に引き継ぐべきかわからない場合はここで相談しましょう
-
- 代わりの人員確保の必要性などについて、意見があれば伝えます。ここは上司が考えるべきところなので、わからない場合は飛ばしても構いません
-
- 現在の体調について伝えます。とくに問題なくこれまで通りの勤務が可能な人は、その旨を伝えましょう
-
- 医師からの指導などがあればしっかり伝えます。必要に応じてここで母健連絡カードを渡しましょう
-
- あなたの休業などで影響を受けるチームメンバーや同僚に対する配慮を伝え、今後のコミュニケーションについて相談しましょう
職場に妊娠を報告するときの注意点
妊娠を報告する状況は人それぞれです。妊娠のタイミングも、自分の体調も、周囲の反応もコントロールできるものではないので、報告するのに不安を感じている人もいるでしょう。でも、ほとんどのことは気に病んでも仕方のないことです。
そうは言っても何も対策ができないわけではありません。業務の引継ぎや周囲との人間関係を円滑に保つために、妊娠を報告するときは以下の2点を意識してみてください。
あまり感情を交えず、事実と事務的な連絡事項をしっかりと伝える
妊娠の報告をするときは、業務を滞りなく進めるために必要な事実と、連絡事項を中心にしっかりと伝えましょう。
周囲の人に迷惑をかけてしまうのではないかと、必要以上に恐縮することはありません。妊娠の報告にネガティブな印象を持たせてしまうと、後に続く人が報告しづらくなるためです。
一方で、個人的な喜びを前面に出すこともおすすめできません。自分の業務が増えてしまうのではないかと不安を感じている人や、子どもを望んでもなかなか叶わない人など、複雑な心境の人が周囲にいるかもしれないためです。
妊娠というプライベートな事実を話すのに抵抗がある人もいるかもしれませんが、職場への報告は、家族への報告とはちがってあくまで仕事の一部です。あまり感情は出さず、普段の業務での報告と同じようなトーンで伝えるとよいでしょう。
相手の心情に配慮し、理解やサポートへの感謝を伝える
妊娠を報告する相手の心情を考え、業務に影響が出ることへの申し訳なさや、理解やサポートへの感謝などをしっかり伝えましょう。
妊娠・出産は自然なことで、従業員の妊娠・出産に対応して業務を調整するのは会社側の役割です。とはいえ、一時的な業務増などで、周囲の人が影響を被ることがあるのも事実です。産休や育休は当然の権利という態度で受け取るよりも、周りの人の感情に配慮した態度を取ったほうが、相手の受け入れはスムーズなはずです。
なお、あなたがこのタイミングで妊娠したことに対して、責任を感じる必要はまったくありません。あくまで業務への影響に対するものとして、お詫びや感謝の言葉を気軽に伝えて、気持ちのよいコミュニケーションを心がけましょう。
よくある質問
最後に、職場への妊娠報告に関してよくある質問と、キャリアアドバイザーからの回答をご紹介します。
Q.1リモートワークが中心のため、対面で伝える機会がなかなかありません
上司に会う機会がない場合には、できればビデオ通話や電話などで伝えるのがいいでしょう。
急いで伝える必要がある場合は、まずはメールやメッセンジャーでも問題ありません。ただし、その後、上司にいろいろと動いてもらう必要があるので、後日あらためて時間を取ってもらい、口頭でていねいに伝えるようにしてください。
Q.2体調不良が激しい場合、その時点で報告してもよいか?
周囲から見て明らかに体調が悪い状態が続いていたり、出勤できない状況が続いていたりするときは、早めに妊娠を報告しましょう。感染症など別の病気を疑われて周囲を不安にさせてしまったり、あなたが望まない形で妊娠のうわさが広がってしまったりするリスクを避けるためです。
妊娠の経過は一人ひとり異なり、予測ができないものです。たとえば職場で体調が急変して倒れたとき、あなたが妊娠していることを誰も知らなければ、すぐに適切な処置を受けられないかもしれません。自分の周囲も安心して働けるよう、早めに報告したほうがいいでしょう。
職場での妊娠報告の重要性と心構え
この記事では、妊娠を職場に報告するときに必要な準備や心構えについて、基本的なことをお伝えしてきました。業務の状況や、上司・同僚との関係性、報告する時点の体調などは人それぞれ異なるので、この記事はあくまで一つの参考情報と考え、あなたの状況にあわせて活用してください。
職場への妊娠報告を控えて、どんな反応が返ってくるか心配している人も多いと思います。しかし、会社にとって、従業員のライフステージが変化するのは当然のことなので、報告を恐れる必要はありません。何よりも大切なあなたとあなたの子どもの命を守り、出産までの日を安心して過ごすために、それぞれのタイミングでしっかり報告しましょう。
\ 未経験から事務職にチャレンジできる /