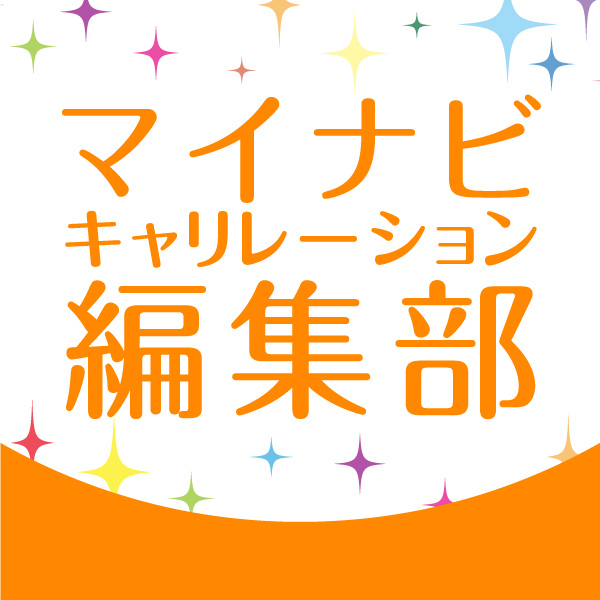【転職】医療事務は「やめとけ」と言われる理由は?仕事内容や向いている人の特徴も解説

医療事務は事務職の中でも身近な地域で求人を見つけやすく、転職先として人気の職種です。しかし、医療事務への転職を検討している人からは、家族や友人から医療事務は「やめとけ」と反対されたり、ネット上で医療事務に関する悪い評判を目にしたりして、不安になったという声を聞くことがあります。
なぜ医療事務に対する悪い評判が存在するのでしょうか。この記事では医療事務は「やめとけ」と言われる主な理由と、実際の業務内容、医療事務に向いている人の特徴などについて、詳しく解説していきます。
目次
医療事務は「やめとけ」と言われてしまう5つの理由
医療事務を目指す人に「やめとけ」と言う人の多くは、自分や家族・友人などが医療事務の仕事を選んで後悔した経験やエピソードをもとに、善意でアドバイスしています。では、医療事務の仕事の大変さはどのような点にあるのでしょうか。
ここでは医療事務は「やめとけ」というアドバイスの根拠としてよく挙げられる5つの理由をご紹介します。
1業務範囲が広い
1つ目は、担当する業務範囲が広く、求められる知識や能力も業務ごとに異なるという点です。簡単な仕事だと思って応募したら、実際の業務は思ったより難しくて後悔した、という経験をした人にとっては、医療事務は「やめとけ」と言いたくなる仕事なのかもしれません。
医療機関で働いたことがない人が、「医療事務」という言葉から最初に想像する業務は受付や会計ではないでしょうか。しかし、実は医療事務が担当する業務は幅広く、電話応対や患者さんの呼び出し、カルテやレントゲンの準備など医師のサポート、入院手続きなども行っています。また各種健康保険組合に診療費用を請求する「レセプト業務」には、医療や保険制度に関する専門知識が必要で、作業の正確性やスピードも求められます。
2人間関係が難しい場合がある
医療事務は基本的にチームで行う仕事なので、職場によっては人間関係で苦労する場合もあります。とくに小さなクリニックでは異動もなく、限られたメンバーと毎日顔を合わせて仕事をすることになります。その中に相性の悪い人がいたり、うまく職場の雰囲気になじめなかったりすると、たとえ業務自体は嫌いでなくても仕事にストレスを感じてしまうことがあります。
ただし、人間関係の良好なクリニックもあれば、医療関係の仕事でなくても人間関係に問題を抱えることはあります。職場によって状況が異なるので、医療事務はほかの職種よりも人間関係が難しい、と決めつけるのは間違いです。
3残業が発生する場合がある
事務職は残業が比較的少ないと言われている職種ですが、医療事務は残業が発生する場合もあります。そのため、ワークライフバランスを重視して医療事務への転職を考えている人には、医療事務の経験者が「実際はブラックだからやめとけ」とアドバイスしてくるかもしれません。
受付や会計を担当している場合、診療が長引いたら患者さんが帰るまで待機しておく必要があります。また、レセプト業務は毎月決まった時期にデータ入力や書類作成の作業が集中するため、対応する人数や業務量によっては、連日残業が発生する可能性もあります。
求人に応募する前に、残業の有無や休日の取りやすさなどを口コミなどでチェックしておくことで、残業の多い職場を回避することはある程度可能です。
4給与が低いと感じてしまう
医療事務の給与はほかの事務職と比べてやや低い傾向があるため、周囲から「給料が低いからやめとけ」と言われてしまう場合があります。なお、医療事務の平均時給は1,401円。平均月収は207,718円、平均年収は3,070,574円です*。
医療事務の平均給与が低い要因としては、アルバイトやパート、派遣社員での求人が多いことが考えられます。これは裏を返せば、柔軟な働き方ができるというメリットでもあります。フルタイムの仕事を選べばキャリアアップや給料アップの道はあるので、平均給与だけを判断基準にして「医療事務はやめておこう」と判断するのはおすすめしません。
※マイナビワークスが保有している膨大な求人データから、医療事務の平均年収、平均月収、平均時給を割り出した金額(2024.11.11時点)
5患者さんとのコミュニケーションやクレーム対応がある
医療事務の仕事では、患者さんや医師とのコミュニケーションが必須です。もしあなたが「コミュニケーションは苦手だけど事務職ならできそう」と思って医療事務を目指しているなら、周囲の人は「やめとけ」と言うかもしれません。
医療事務の仕事の中で、1人でパソコンや書類と向き合って完結する業務はそれほどありません。受付業務やクラーク業務では頻繁にコミュニケーションが発生し、ときには患者さんからのクレームを受けることもあります。患者さんとのコミュニケーションという面では、医療事務は一般的な事務職のイメージよりも、接客業に近いと考えたほうがいいかもしれません。
医療事務の仕事内容とは?
医療事務への転職は「やめとけ」と言われてしまう要因の1つに、業務内容とのミスマッチが挙げられます。実際に働いてみたら思ったよりも難しかった、自分には向いていなかった、という事態を避けるには、医療事務の仕事内容をしっかり理解しておきましょう。
ここでは、医療事務の主要な業務を3つ、簡単に紹介します。より詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
1患者さんにいちばん身近な受付・会計業務
私たちが病院に行ったとき最初に接するのが、受付業務をしている医療事務担当者です。受付業務では、患者さんから保険証を預かったり、診療申込書を書いてもらったり、受診科への案内をしたりします。また初診の患者さんの診察券発行やカルテ作成を行い、再診の患者さんに対する予約管理なども行います。
会計業務では、診療費を計算して明細書を作成し、患者さんが負担する分のお金を支払ってもらいます。不調や不安を抱えた患者さんと接する機会が多いため、ていねいな対応や細かい気配りが求められる仕事です。
2患者さんと医療スタッフのかけ橋となる、クラーク業務
医師や看護師などの医療スタッフの事務作業全般をサポートする業務を「クラーク業務」と呼び、「外来クラーク」「病棟クラーク」の2種類があります。
外来クラークでは、来院した患者さんを診察室に案内したり、カルテや検査結果書類の準備をしたりして医師の診療をサポートします。病棟クラークでは、入退院の手続きや、手術・検査スケジュールの管理、各種書類作成、面会者への対応などを行います。
医療事務はクラーク業務を通じて、医療スタッフが診療に集中できる環境を作り、病院の円滑な運営を支えています。
3医療事務の専門性で病院経営を支える、レセプト業務
レセプト業務は病院経営に欠かせない業務の1つで、医療事務の専門性が最も求められる仕事です。
行われた処置や使用された薬に応じた診療報酬点数(1点が10円の診療費用を表す)を、患者さんごとに1ヵ月分まとめて記載した書類のことをレセプト(診療報酬明細書)といいます。これを作成して健康保険組合などに提出し、診療費用の請求を行うのがレセプト業務です。
レセプト作成には医療や診療報酬制度に対する専門知識が必要です。レセプトの作成・点検・提出は毎月限られた期間に行う必要があり、内容に間違いがあると再提出や減額の対象となることがあるため、作業にはスピードと正確性の両方が求められます。
医療事務は「やめとけ」の理由を払拭する、医療事務の魅力4選
医療事務に限らずどの仕事でも同じですが、仕事にはメリットとデメリットの両面があり、ある人にとってはデメリットでも、角度を変えて見ればメリットになる場合もあります。
ネット上などではネガティブな意見が注目されてしまいがちでも、実際には、医療事務の仕事に魅力を感じて働き続けている人が大勢います。ここからは、医療事務の魅力を4つご紹介していきます。
1資格がなくてもチャレンジできる
医療事務は、医師や看護師などの医療スタッフとはちがい、特別な資格や学歴が必要ありません。未経験者可の求人も多いため、接客業などほかの職種からの転職や、子育てなどでしばらく仕事を離れていた人の再就職先としても人気です。資格や経験がなくてもチャレンジできることは、医療事務の大きな魅力と言えるでしょう。
なお、資格は医療事務として働くうえで必須のものではありませんが、資格があれば業務に対する理解度が上がり、採用や給与の面でプラスになる場合もあります。
医療事務でおすすめの資格
医療事務には国家資格はありませんが、民間の資格や検定が数多く存在します。医療事務としてのキャリアアップを目指したい方や、少しでも有利な条件で転職活動をしたい方は、医療事務の分野でメジャーな資格や検定への合格を目指すとよいでしょう。
おすすめは「診療報酬請求事務能力認定試験」や「医療事務技能審査試験」です。医療事務に役立つ資格について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
2医療がある限り必要な、将来性のある仕事
職場が身近にあり、求人が多いというのも魅力の1つです。人が住んでいるところには全国どこでも医療機関があります。家の近くで働くことができ、引っ越した先でも仕事を見つけやすいのは、医療事務として働く大きなメリットと言えるでしょう。
生成AIの発達によって医療事務の仕事がなくなるのではないか、と心配している人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。たとえAIの力で医療事務の仕事が効率化されたとしても、医療事務の仕事を理解してAIに指示を出したり、AIが出力した結果をチェックしたりする人は必要です。
少子高齢化により、働き手が減る一方で医療の需要は高まっています。医療が必要とされる限り医療事務も必要とされ、将来性の高い仕事と言えるでしょう。
3さまざまな人から感謝をもらえる
さまざまな人から感謝され、社会に役立っていることが実感できるのも医療事務の魅力です。一般的に事務の仕事は「縁の下の力持ち」的な役割が多く、あまり組織の表側には出ないものです。しかし医療事務の場合は、「組織の顔」と言えるほど、患者さんやその家族とコミュニケーションする機会が多くあります。
体調不良で困っている患者さんや、不安な思いをしている患者さんの家族と接してサポートし、医療スタッフの仕事が円滑に進むようにすることで、医療を通じて社会を支えるやりがいを実感できるはずです。
4医療知識だけではなくPCなど幅広いスキルが身に付く
医療事務として働くと、医療保険制度についての専門知識が身に付きます。さらに、医療事務の業務はパソコンを使ってデータ入力をしたり、対面や電話での患者さん対応をしたりと幅広いため、事務に関する汎用的なスキルが身に付くメリットもあります。
パソコンスキルやコミュニケーションスキルは、事務に限らずさまざまな仕事で必要とされます。将来的に医療事務以外の仕事にキャリアチェンジする際にも役立つでしょう。
医療事務に向いている人の3つの特徴
医療事務の仕事にメリットが多いと感じるか、デメリットが多いと感じるかは、あなたが医療事務に向いているかどうかによっても変わってきます。
下に紹介する3つの特徴に当てはまる人は、きっと医療事務の仕事に魅力を感じることができるでしょう。
医療事務に求められるスキルや適性について、詳しくはこちらの記事もご覧ください。
1人とコミュニケーションをとるのが好きな人
初対面の人と話すことや、チームで仕事をすることが得意な人、コミュニケーションに苦手意識のない人は医療事務に向いています。
病院にはさまざまな人や患者さんがやってきます。医療スタッフにもさまざまなタイプの人がいます。相手の言葉や表情から的確にニーズを読み取り、状況に合わせて対応できる人は、医療事務の仕事をスムーズにこなすことができるでしょう。
2どんな細かい作業にも責任をもって取り組める人
細かい作業が得意な人、責任感を持ってミスなくやり遂げられる人は、医療事務に向いています。
カルテ作成やレセプト作成など、医療事務には細かい入力作業やチェック作業がたくさんあります。これらの事務書類は、患者さんの健康や病院の収入に影響するものなので、ミスは許されません。注意深く作業することはもちろん、不明点があれば関係者への確認や問い合わせをするなど、責任を持って仕上げることが求められます。
3知識を蓄えるのが好きな人
勉強が苦にならず、情報を集めて知識を蓄えることに喜びを感じられる人も、医療事務に向いています。
医療事務に関する知識は、一度勉強して覚えたら終わり、ではありません。医療保険制度は頻繁に改正されるため、その都度あらためて勉強し、知識をアップデートする必要があります。医療事務の仕事を続けるには、医療保険をめぐる世の中の動きに情報感度を高くして、勉強し続ける姿勢が求められます。
よくある質問
最後に、医療事務への転職希望者からよくある質問と、マイナビキャリレーションのキャリアアドバイザーからの回答をご紹介します。
Q.1本当に未経験からでも働けますか?
医療事務の仕事には特別な資格が必要なく、未経験者も応募できる求人は多数あります。
医療事務の仕事の中でも割合が大きい「受付・会計業務」では、飲食店やアパレルなどの接客業と同様に、コミュニケーションスキルが求められます。そのため、接客業の経験者が歓迎される場合もあります。
Q.2転勤などが発生する可能性はありますか?
地域密着のクリニックや病院であれば、転勤などは基本的にないと考えていいでしょう。
ただし、多数の関連施設を持つ医療法人グループに所属する場合は、転勤がないとは言い切れません。応募する際に勤務条件をしっかり確認してください。
医療事務の魅力と自分の適性をよく考えて、転職するか判断しよう
医療事務は、「やめとけ」という声がある一方で、魅力的な要素も多い職種です。医療事務への転職を考えている方は、ネガティブな面だけでなくポジティブな面も知ったうえで、自分が医療事務に向いていそうかどうかを考えてみてください。
自分が医療事務に向いているかどうかがわからない方や、未経験で自信がない方には、無期雇用派遣の制度を利用するのもおすすめです。マイナビキャリレーションなら、専属のキャリアアドバイザーがあなたに合った就業先をご提案させていただきます。詳しくはこちらの記事もご覧ください。
\ 未経験から事務職にチャレンジできる /