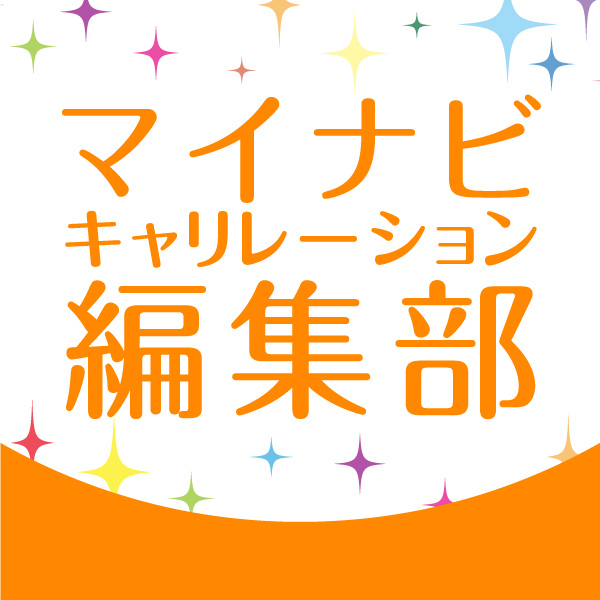「ワークライフバランスとは?」転職で人生をもっと充実させるための基礎知識

ワークライフバランスは、仕事や働き方を選ぶ際に大切な要素です。
どれだけ仕事が充実していても、激務で健康を害したり、大切な人と過ごす時間が取れなくなったりするような働き方だったら、長く続けることはできません。
この記事では、就職や転職を考えるときにぜひ知っておきたい「ワークライフバランス」の考え方や、ワークライフバランスを整えるメリットについて解説していきます。
目次
ワークライフバランスとは?
ワークライフバランスとは、「仕事と生活の調和」という意味です。調和とは、複数のものが衝突したり矛盾したりすることなく、釣り合いがとれてまとまっている状態のことを指します。仕事か生活、片方のためにもう片方を犠牲にしなければならないような状態であれば、調和しているとは言えません。仕事と生活の両方に満足できているのであれば、「ワークライフバランスが取れている」状態と言えます。
ワークライフバランスについて考えるときに気をつけたいのは、「仕事と生活の時間を半々にすればいい」といった単純な話ではないことです。
理想のワークライフバランスは一人ひとり違い、同じ人でも時期や状況によって求めるバランスが変化します。たとえば、「多少プライベートを犠牲にしても、はやくキャリアを構築したい」という時期もあれば、育児などのライフイベント、自分自身の健康状態などによっては、「今は仕事のペースを落としてプライベートを優先したい」という時期もあるでしょう。
内閣府での「ワークライフバランス」の定義
国や経済界もワークライフバランスの推進に取り組んでいます。
日本では2007年に内閣府の男女共同参画局が、経済界・労働界・地方公共団体の代表等からなる「官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」・「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を策定。2010年にはこれらに新たな視点や取り組みが加えられ、あらためて合意が結ばれました。
内閣府の男女共同参画局による「仕事と生活の調和」推進サイトでは、ワークライフバランスが求められる社会的な背景について述べたうえで、「仕事と生活の調和が実現した社会の姿」は以下のようなものであるとしています。
仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」である。
さらに、目指す社会の具体的な姿や、それを実現するために企業や働く人、国などの関係者が果たすべき役割について具体的に書かれています。興味のある方は読んでみてください。
現在、ワークライフバランスは企業も積極的に推進している
ワークライフバランスの推進は、企業と働く人の両方で取り組むものです。少子高齢化社会で採用難に悩む企業にとっては、優秀な人材を採用・育成し、働き続けてもらうためにも、ワークライフバランスの推進が欠かせません。
ワークライフバランスに力を入れることは企業の生産性や利益によい影響を与えるという調査結果もあり、自社の競争力向上のためにも従業員のワークライフバランスに力を入れる企業が増えています。以下に、2社の事例をご紹介します。
多様で柔軟な働き方を会社がサポート P社
それぞれの状況やニーズに合わせた働き方が選択できる柔軟な勤務制度を導入しています。1日の勤務時間を増やすことで週休3日を選択したり、月あたりの勤務時間を減らして週休4日したりすることが可能です。また、リモートワークを活用することで、通勤圏外に在住していても働くことが可能です。
これらの制度は、育児中や介護中、パートナーの転勤への帯同、自己学習やボランティア活動、社外副業など、目的を問わずに利用することができます。
出勤・退勤時間は自由選択、退職者への出戻りサポートも O社
コアタイムを設けず、平日・土日祝日を問わずに出勤・退勤時間を自由に設定できる「スーパーフレックス制度」を導入。結婚記念日や家族の誕生日等に特別休暇を取得できるほか、四半期ごとに 4~8 日程度連休をとれる制度もあります。
家庭の事情等で退職した社員が復職しやすいよう、一定の貢献をした社員は退職2年以内であれば同じ役職・条件で再就職ができる「出戻り手形」を発行。キャリア3年以上の社員が退職後に再入社する際は支度金を支給して歓迎しています。
ワークライフバランスを整えることで得られるメリット
ワークライフバランスを整えることは、働く人にとってさまざまなメリットがあります。
ワークライフバランスを意識しなければ、ワークの割合が重くなりすぎて身体的・精神的に辛くなる、ライフに充てる時間が長くなりすぎて業務との折り合いがつかなくなるなど、結果として仕事を続けられなくなってしまう場合があります。
そうならないためには、自分の健康や家庭の状況、やりたいことや目指したいこと、そのために必要な収入や時間について考え、その時々の自分に最適なワークライフバランスを選び取っていくことが大切です。
ワークライフバランスを整えるには、自分で考えるだけでなく、家族や職場の上司との相談、会社や国などが用意した制度の利用、場合によっては異動希望や転職なども視野に入れる必要があるでしょう。簡単ではないかもしれませんが、ワークライフバランスを整えることで以下のようなメリットを得ることができます。
仕事にメリハリがでる
仕事と私生活の両方を充実させるには、限られた時間で効率的に業務をこなさなければなりません。そのためには、ワークに使える時間とそれぞれの業務の期限を常に考える必要があるため、オンとオフのメリハリをつけながら仕事をする習慣がつきます。
オンとオフを意識することで、「どうしたら時間内に仕事を終わらせるか」という工夫に繫がりやすくなります。また、プライベートで得た知見を仕事に生かしたり、仕事で得た知見をプライベートに生かしたり、といった相乗効果も得やすくなります。
プライベートの時間をしっかり取ってリフレッシュすることで、仕事にもよい影響を与えるでしょう。
プライベートの自由度が上がる
ワークとライフの割合をしっかり決めることで、プライベートの自由度が上がるというメリットもあります。
ワークとライフの境目をあいまいにしていると、ついライフの時間にワークが浸食してくることがよくあります。たとえば、休日にも仕事のことが気になってメールに返信してしまう、業務時間外に取引先や上司から電話がかかってくる、などです。
その点、ワークとライフの配分を明確にして「この日の業務はここまで」「○曜日は休日」と周囲にしっかり宣言しておくことができれば、プライベートの時間は仕事から完全に離れて、より自由に過ごすことができます。
心身に余裕が持てる
ワークとライフをうまくバランスさせることで、心身に余裕が持てるというメリットもあります。
ワーク中心の生活になってしまうと、十分な休息が取れずに疲弊したり、仕事以外の時間にも仕事のことが頭から離れず精神的に参ってしまったりすることがあります。しかし、あらかじめライフの時間をしっかり確保しておけば、心身を疲弊させることなく、ゆとりを持って生活することができます。
一方、ライフ中心の生活であっても、家庭内で育児や介護などのケア役割を担っていると、自分のペースで過ごせる時間が持てないうえに、ケアに費やした時間や労力に対して見返りが得られないなど、心身の余裕がなくなることがあります。その場合は、ワークの時間を確保することで、仕事を通じて達成感や評価、報酬を得たり、通勤時間や休憩時間に1人で息抜きする時間を持ったりできることがメリットになります。
ワークかライフのどちらかではなく、両方を選ぶことで得られる効果があるのです。
中長期的なライフプランを設計できる
ワークかライフどちらかではなく両方を選ぶことは、中長期的なライフプラン設計をする際にもメリットがあります。
仕事には常に全身全霊で取り組まなければならないと考えると、健康や家庭の問題でそれができなくなったときは「退職する」または「無理をしてでも働き続ける」という選択肢になってしまいます。結婚や出産、自分や家族の健康状態など、将来どのようなタイミングで何が起こるかはわからず、貯蓄や扶養者がいない状態で退職すれば困窮する恐れもあるため、将来がとても不透明で不安な状態です。
しかし、ワークとライフの割合を調整しながら働き続ける選択肢があれば、ライフステージの変化に対応しながら収入を確保し、無理なく生活を続けるライフプランを立てることができます。先を見通すことで自分のやりたいことや、進みたい方向性も見極めやすくなるでしょう。
事務職はワークライフバランスを安定させやすい職業
ここまで読んで、自分の現在のワークライフバランスに疑問や危機感を感じた方もいるのではないでしょうか。もし、自分の求めるワークとライフのバランスが今の仕事では実現できないと思うのであれば、転職という選択も考えられます。
どちらかというとライフ重視で、「残業はできるだけ避けたい」「日中の勤務で、土日祝日は休みになる仕事がいい」「体力的にきつくなくて、長く続けられる仕事がいい」という方におすすめの仕事は、事務職です。
一般的に事務職はオフィス内で座って行う仕事が大半で、定型業務が中心のため計画が立てやすく、残業も少ないという特徴があります。業務を通じて基本的なビジネスマナーやパソコンスキルが身に付くため、将来的にキャリアチェンジをする際にも事務職での経験が役立ちます。
ワークライフバランスの安定を求めて転職を考えるなら、事務職を検討してみてはいかがでしょうか。
マイナビキャリレーションで事務職にチャレンジ
事務職は、転職市場で人気があり、競争率が高くなりやすい職種です。そのため、なかなか未経験者OKの求人が見つからなかったり、応募しても競争率が高くて受からなかったりする場合があります。
でも、たとえ事務職としての実務経験がなくても、あきらめる必要はありません。無期雇用派遣という制度を使ってチャレンジする方法があります。無期雇用派遣とは、一般的な登録型派遣とは異なり、働く人が派遣会社と期間の定めのない労働契約を結び、安定した雇用条件のもと、派遣先企業で働く制度です。
未経験者であっても一定の条件を満たしていれば、派遣会社が提供するキャリア支援や研修などを利用しながら必要なスキルを身に付けて、事務職としての一歩を踏み出すことができます。
実際にマイナビキャリレーションで働いている人の声
マイナビが運営する無期雇用派遣サービス「マイナビキャリレーション」では、大勢の先輩が無期雇用派遣スタッフとして、さまざまな業界で事務職デビューを果たしています。その中には、派遣先企業から直接雇用のオファーを受けて、正社員に転換した人も少なくありません。
実際に働いている人の声をこちらで紹介していますので、ぜひご覧ください。
よくある質問
最後に、ワークライフバランスについて転職希望者からよくある質問と、マイナビキャリレーションのキャリアアドバイザーからの回答をご紹介します
Q.1「ワークライフバランス」か「ライフワークバランス」、どちらが正しい表記ですか?
辞書や辞典などに収録されている一般的な表記は「ワークライフバランス(Work-Life Balance)」です。内閣府のWebサイトや資料では「ワーク・ライフ・バランス」と、区切って表記されています。
仕事よりも生活を強調するために「ライフワークバランス」と表記される場合もありますが、あまり一般的ではありません。転職活動や仕事の場面では「ワークライフバランス」または「ワーク・ライフ・バランス」と表記するのがよいでしょう。
Q.2面接の場において、ワークライフバランスについては聞いてはいけないのでしょうか?
絶対にNGというわけではありませんが、聞き方には注意が必要です。制度や福利厚生のことばかりを質問すると、自分の都合ばかりを考えているという印象を与えかねないためです。
企業側は、自社の事業や業務に関心があり、自社の文化とマッチ度の高い人を採用したいと考えています。たとえば、応募先企業の業務内容や文化に関心を示しながら「現状の社員のワークライフバランス」や「よく利用されている制度」などについて質問するのであれば問題ないでしょう。
ワークライフバランスについて考え、周囲の人と話してみよう
ライフステージが変化しても働き続けるためには、ワークライフバランスを意識することが大切です。仕事や家庭、自分自身の健康などの状況は人それぞれなので、必ずしも理想が叶えられるとは限りませんが、まずは自分がどうしたいのかを考えることが、ワークライフバランスの安定に向けた第一歩です。
働く人のワークライフバランスは、さまざまな関係者が協力しながら確保するものです。ぜひこの記事を参考にご自身のワークライフバランスについて考え、周囲の人と話をしてみてください。
\ 未経験から事務職にチャレンジできる /